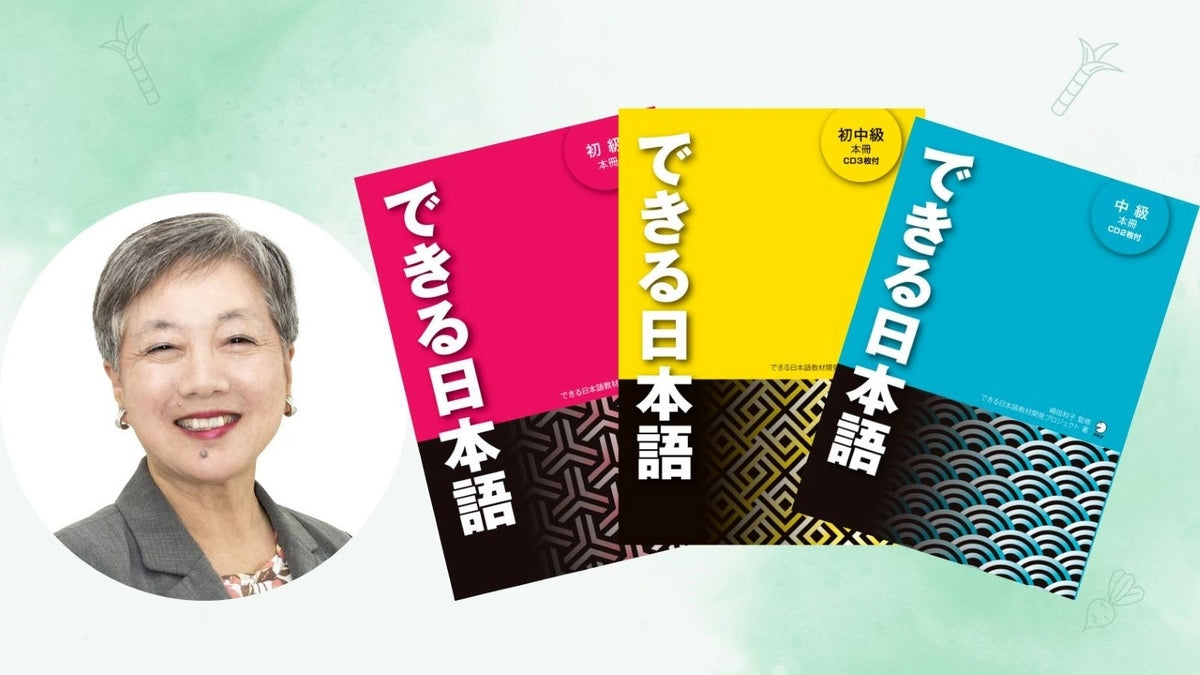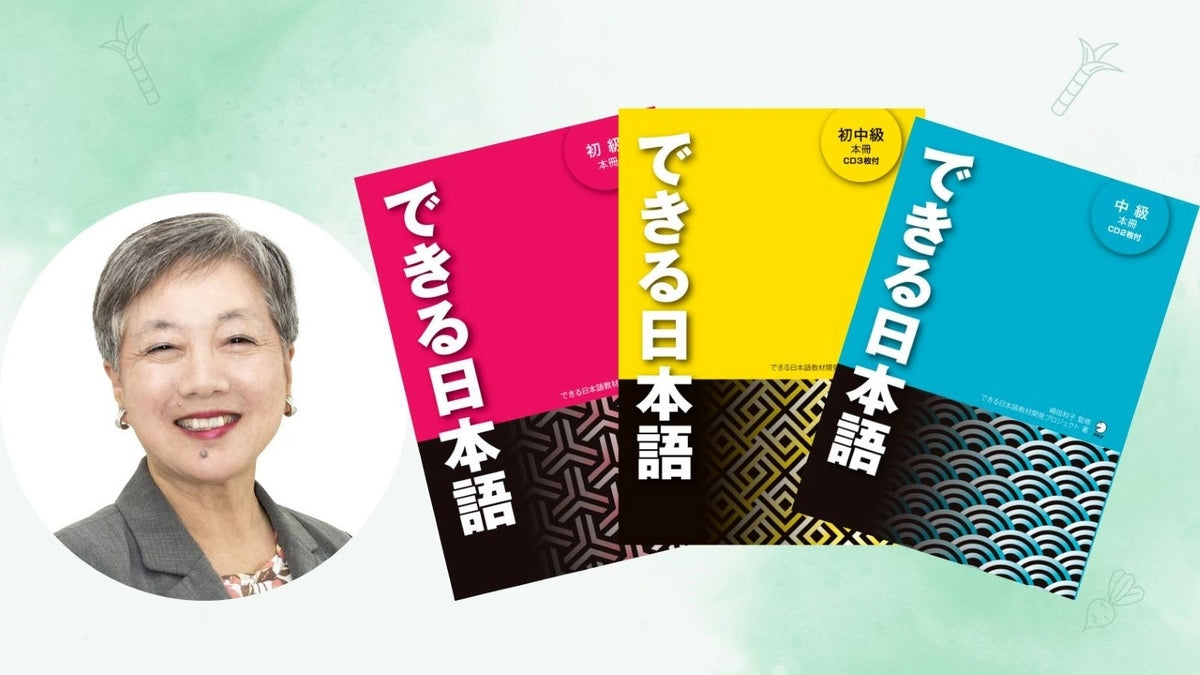外国語の会話能力を測る国際的なテストであるACTFL-OPI。アルクでは30年前からワークショップを行い、OPIの日本語試験官(インタビューアー)を養成してきました。今では1000名以上の方がワークショップを受講し、国内外の日本語教育機関で活躍しています。
本記事ではOPI(Oral Proficiency Interview)の基本的な考え方を紹介します。
シンポジウム「日本語OPIが切り拓く新たな日本の社会」(2019年4月7日、東京)で行われた講演「OPIの魅力とインパクト」(鎌田 修 氏、南山大学元教授)の一部を、編集部が再編しました。
OPIとは? 会話能力とは?
OPIとは外国語の「会話能力」を測るテストです。では、会話能力とは何でしょうか。
それは、「現実の生活場面における言語運用力」ということになります。また、OPIは中間・期末テストのような達成(アチーブメント)テストではなく、リハーサル(事前練習)したものを披露するようなものでもありません。いつ、どこで外国語を学んだのかを問わない、真の実力テストということになります。
現実に試験官の目の前でインタビューを受けて、各個人、何がどのぐらいできるかを測るテストなのです。
OPIの具体的な手順
OPIの実際のインタビューは以下のような手順で行われます。
- ウォームアップ
- 下限(フロア)探し
- 上限(シーリング)探し
- ロールプレイ
- ワインドダウン
2と3の間で、どのレベル(初級・中級・上級・超級)がしっかり維持できているか、あるいは上のレベルでも対応できるかできないかを確認(縦フリ)します。その上で、同じレベルで話題を変えた時(横フリ)に維持できるレベルを確認します。
そして、総合的にプロフィシェンシー(言語を使ってどれだけ、どのように、課題を遂行できるかを示すもの。熟達度)レベルを決定します。ここがインタビューにおける最も大切なところです。
縦フリによって、話題を抽象的なもの、馴染みのないもの、複雑なものや、逆に具体的なもの、慣れ親しんだもの、ストレートなものに縦フリしていきます。
そして横フリによって話題を、「イマ」から明日、昨日、来月、先月、来年、去年に、また「ココ」から、そこ、あそこ、家庭、学校、会社に、「あなた」から兄弟、彼・彼女、友達、同僚へと広げていきます。
学習者は接触場面で日本語力を伸ばしている
著名な言語学者であるJ. V. ネウストプニーはこのように言っています。
「外国語教育の目的がその言語の運用能力の育成にあるとするならば、その学習者がどのようにその言語を使用しているかを調べることは外国語教育の出発点であり、到達点でもあろう」『新しい日本語教育のために』(大修館書店)
日本語学習者は、さまざまな「接触場面」を繰り返し経験することによって日本語能力を高めます。この接触場面とは、挨拶する場面であったり、ショッピングをする場面であったり、自分の故郷を紹介する場面であったり、少子化問題について議論する場面だったりします。このような接触場面は初級から超級までいろいろなレベルがあります。
「現実の生活場面における言語運用力」を測ることがOPIの目的であり、教室だけでなく現実社会の接触場面の中で学習者が言語運用能力を伸ばしているとすると、究極の外国語教材とは、
- 生きたもの(本物)
- 面白いもの(個に訴えるもの)
- 遭遇可能性の高いもの
- 力の増すもの
であり、イマ、ココで(目の前にいる)アナタに役立つもの、換言すれば(反語的ではありますが)用意されていない教材をその場に用意することが、プロフィシェンシー志向の外国語教育であるとも言えます。
関連記事
2024年 04月 12日
この春始めたい!日本語教師がちょっと知っていると役に立つ、英中韓以外の外国語は?


この春始めたい!日本語教師がちょっと知っていると役に立つ、英中韓以外の外国語は?
2024年 02月 14日
【連載】教科書について考えてみませんか-第4回 「わかる」から「できる」へ
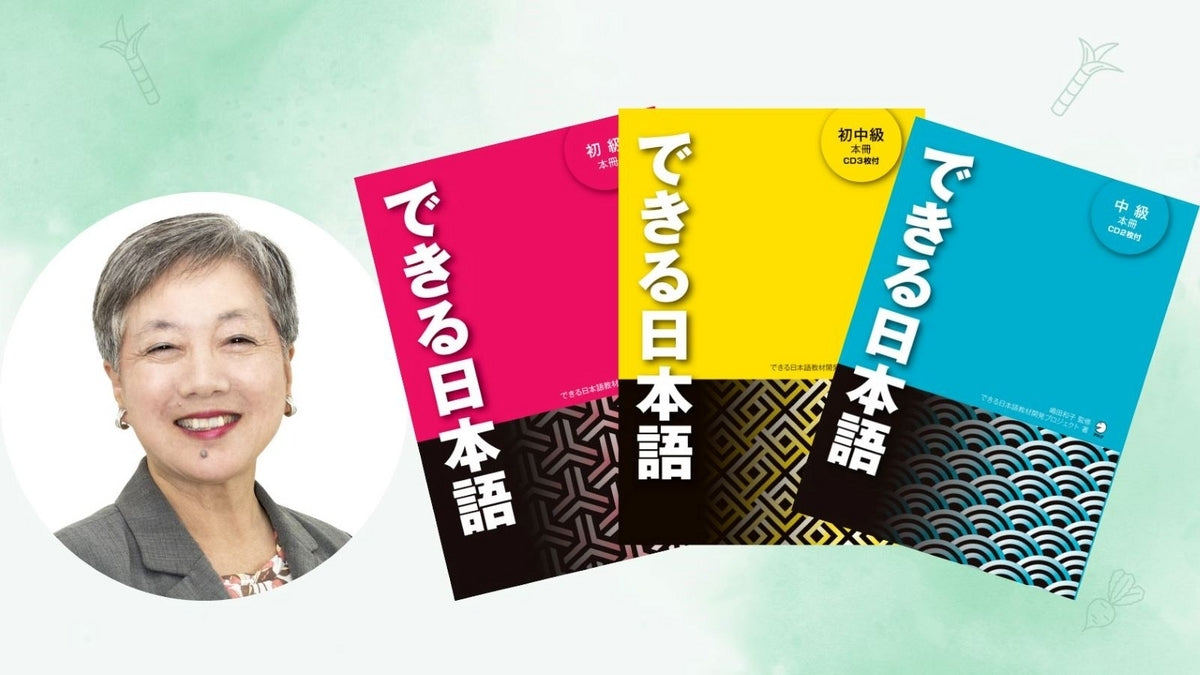
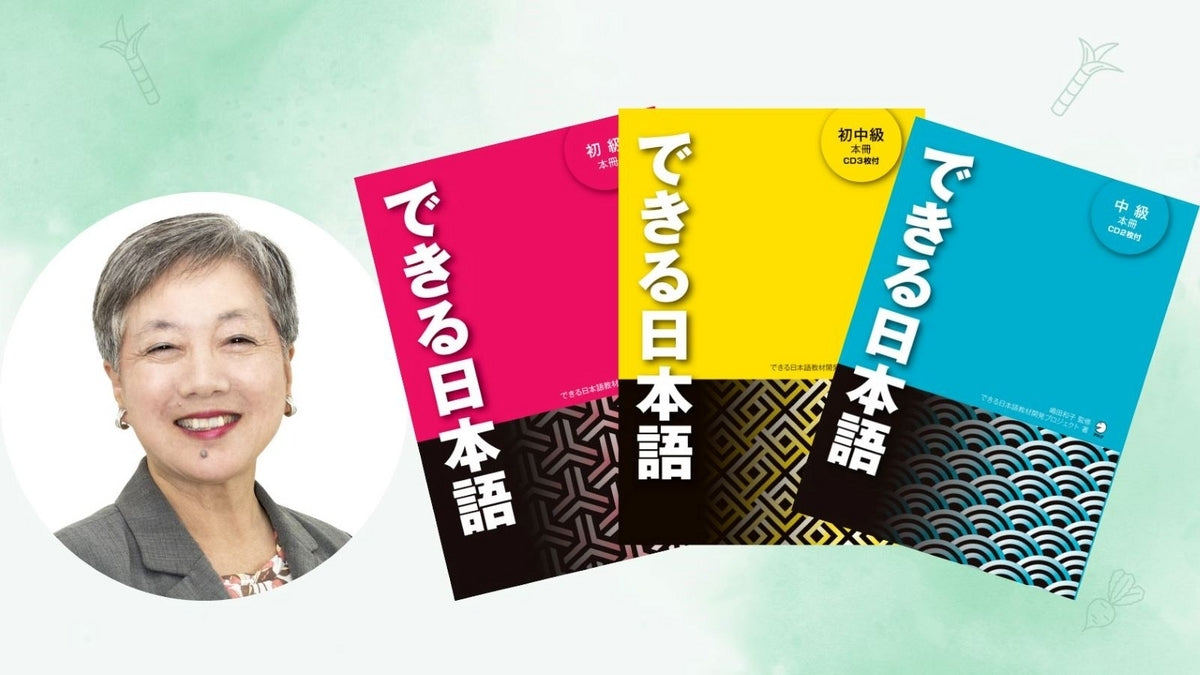
【連載】教科書について考えてみませんか-第4回 「わかる」から「できる」へ
2024年 01月 26日
日本語教師プロファイル嶋田和子さん―主体性と創造性が活かせるこんな楽しい仕事はありません!

2024年最初の「日本語教師プロファイル」インタビューでは、東京都中野区にあるアクラス日本語教育研究所にお邪魔して、代表理事の嶋田和子先生にお話を伺ってきました。日本語教育界にとって一つの変革の年である今年、嶋田先生はどのようなお考えをお持ちか、是非お聞きしたいと思いました。インタビューは嶋田先生の思いとパッションの溢れるものとなりました。...

日本語教師プロファイル嶋田和子さん―主体性と創造性が活かせるこんな楽しい仕事はありません!
2023年 12月 29日
【連載】教科書について考えてみませんか-第3回 タスク先行型授業にチャレンジ!


【連載】教科書について考えてみませんか-第3回 タスク先行型授業にチャレンジ!
2023年 12月 07日
【連載】教科書について考えてみませんか-第2回 どんな教科書と付き合っていますか?